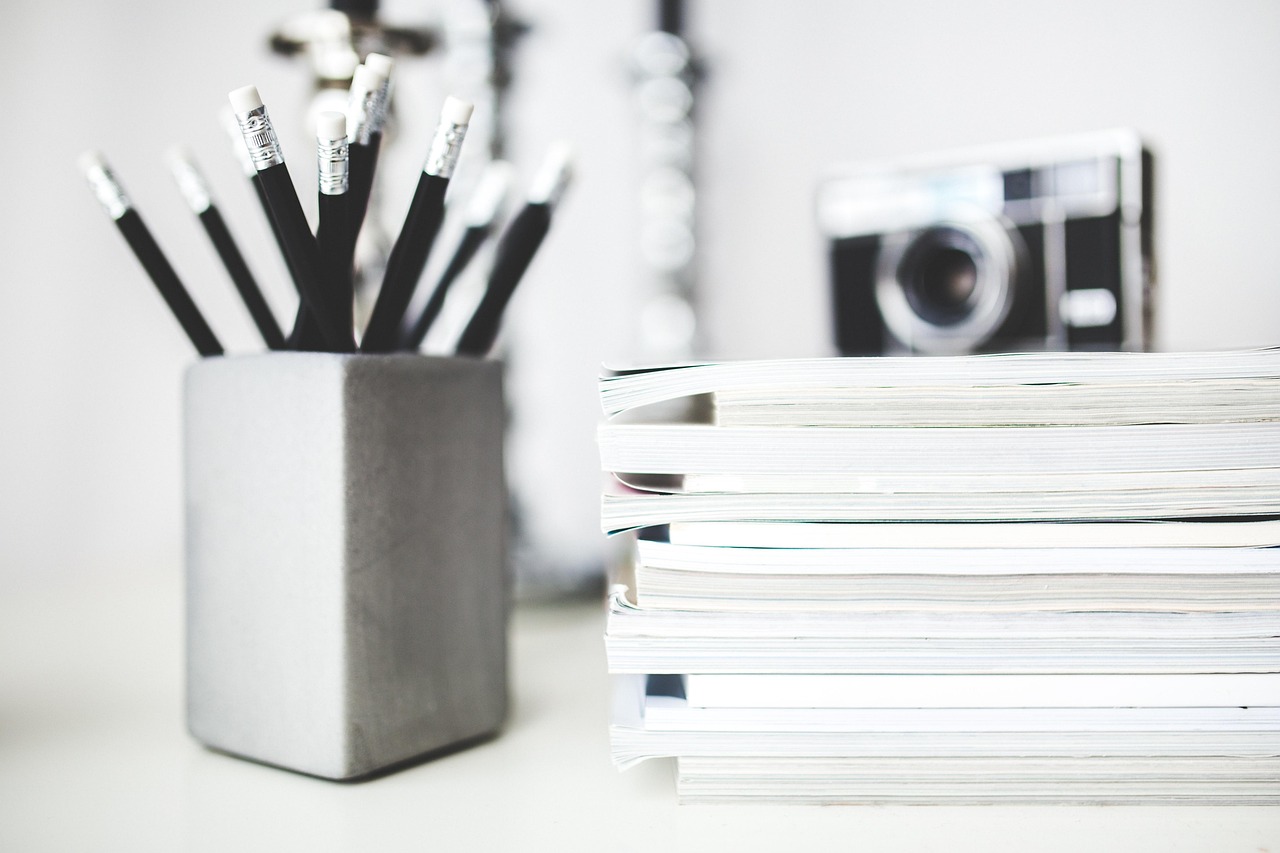「あれ、あの書類どこだっけ?」──
デスクの引き出しをガサゴソしてしまったこと、誰しも一度はあると思います。
総務・事務の現場では、資料を出す、確認する、書類を戻すという作業が延々と続きます。そんな中で、デスクまわりがごちゃごちゃしていると“探す時間”が積み重なって、気づけば何十分もロスしてしまうことも。
今回は「デスク整理」にフォーカスして、ちょっとした工夫で「探し物ばかりの時間」が「スムーズ作業の時間」へと変わる整理術を4つご紹介します。
明日からでも取り入れられるシンプルな方法なので、ぜひ一緒に実践してみてくださいね。
デスク整理|ゾーン分けで使うものだけ机上に置く
まず、デスクを「この場所は使う」「この場所はしまっておく」――とゾーン分けしましょう。
例えば「パソコン作業エリア」「ペン・文房具エリア」「資料置き&処理待ちエリア」というように3つに分けるだけで、作業のモードが切り替わりやすくなります。
実践ポイントとしては:
- よく使うペン・付箋・消しゴムなどは文房具エリアにまとめる
- 資料・ファイルは「処理中」/「保管」などラベル付きでエリアを分ける
- ゾーンごとに必要な道具だけ置く=机上に不要なものを出さない
この仕組みができているだけで、「あれはどこだっけ?」がぐっと減ります。そんなゾーン分けにオススメ文具ガジェットがコチラ↓↓
文房具をまとめて“文房具ゾーン”へ。スタイリッシュな仕様で、机上の“使うものだけ”がひと目で分かるようになります。
デスク整理|引き出し・文房具ケースを「空白あり」で使う
引き出しの中一杯に文房具を詰め込んでいませんか?実はこれは「使いづらさ」を生んでしまう原因になります。デスク引き出しには少し空白の余裕を持たせると、物を戻しやすく次に探しやすいです。
具体的には:
- 文房具ケースに仕切りを入れて「頻繁に使うもの」「たまに使うもの」に分類
- 引き出しの半分ほどを“予備スペース”として空けておく
- 書類トレイやファイル立てを使って、引き出しではなく「縦」に収納
この方法により、引き出しを開けたときに「何がどこにあるか見える」状態が維持できます。結果として探す時間が激減します。そんなときにオススメの文具ガジェットはコチラ↓↓
文具や付箋・書類クリップなどを整理して机の上でも引き出しの中でも”余白を作る”ことができるガジェットです。
デスク整理|書類は「捨てる・保管・処理中」の3箱方式で管理
書類が乱雑になると、デスク上に積み上がってしまい、“探す時間”が悪化します。そこでおすすめなのが「捨てる箱」「保管箱」「処理中箱」の3つで書類を振り分ける方式です。
実務での具体的な使い方:
- 「捨てる箱」:期限切れ・不要な資料を即入れる。日別・週別で捨てる習慣を。
- 「保管箱」:保管が必要な書類。フォルダ・ラベル付けして引き出しまたは棚へ。
- 「処理中箱」:今手を付けている、またはすぐ確認が必要な書類を置く場所。机の手前などアクセスしやすい位置に。
この3箱方式を使うと、「どこにあるか分からない」「どうすべきか迷う」が解消され、書類管理がだいぶラクになります。
トレイ形式で「処理中」「保管」「捨てる」それぞれの箱を設けると、書類の流れが明確に。
デスク整理|“見えない整理”も実は重要
「書類も文房具も整理したけど、机の下や後ろにごちゃっとケーブルが…」という方も多いのでは?実はこういった“見えない混乱”も作業効率に影響を及ぼします。
具体的なアイデアとしては:
- モニタースタンドを使って机下面のスペースを収納に活用
- ケーブルを結束バンドやケーブルボックスでまとめる
- 充電器・延長コードは端に寄せて、机上には極力出さない
- デスク上に置くものを「使うものだけ」に限定し、その他は棚や引き出しへ
こうしておくと「机の上に物がない」=視界がクリアになり、作業の切り替えもスムーズになります。山崎実業towerシリーズのオススメがコチラ↓↓
デスクの裏側・天板下に取り付けてケーブルを整えるラック。ケーブル類を床から浮かせて整理することで、安全性も作業効率も向上します。
デスク整理|まとめ 探す時間が減れば、余裕が生まれる
デスクを整理することは、ただ「見た目をきれいにする」だけではありません。
どういう状態だと“探す時間”が発生するかを理解し、その時間を“作業時間”に変えることが真の目的です。ぜひ今回ご紹介した整理術と整理文具ガジェットをご検討ください。
- ゾーン分けで使うものを決める
- 引き出し・文房具ケースに余白を設ける
- 書類は「捨てる・保管・処理中」の3箱方式で管理
- ケーブル・デスク周りも含めた“見えない整理”
これだけでも、明日からのデスク周りがグッと楽にスッキリするはずです。